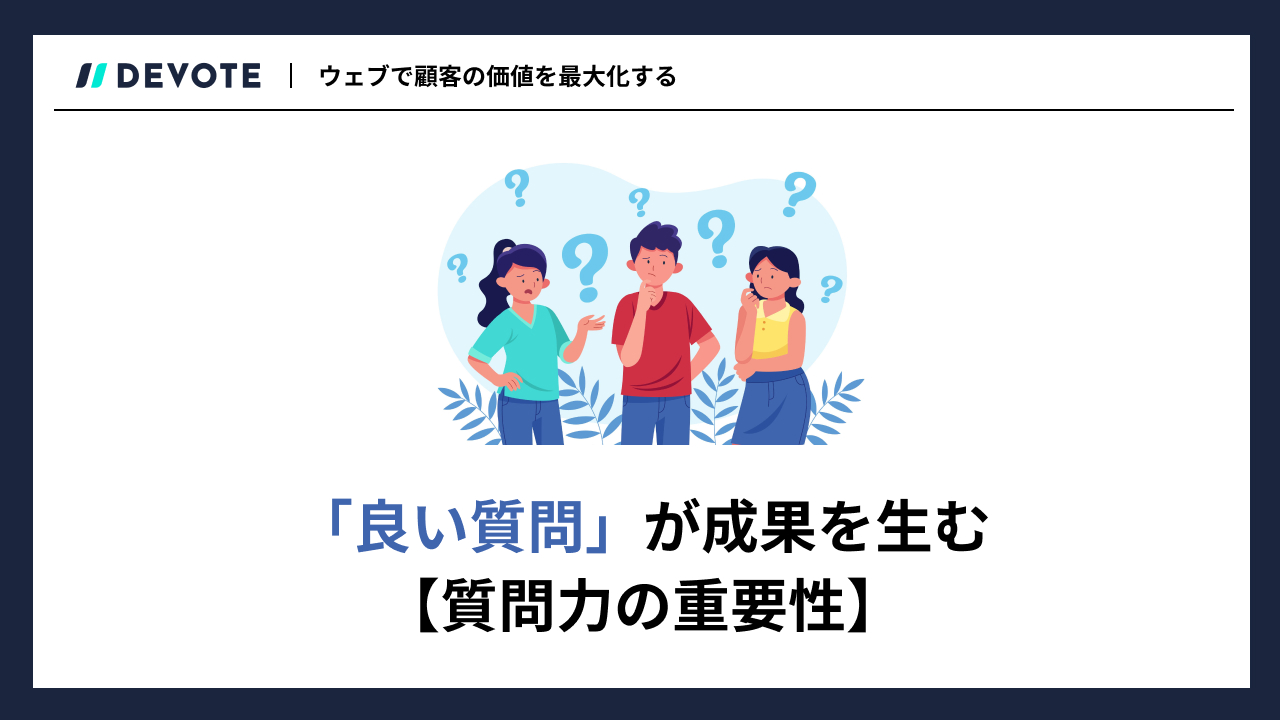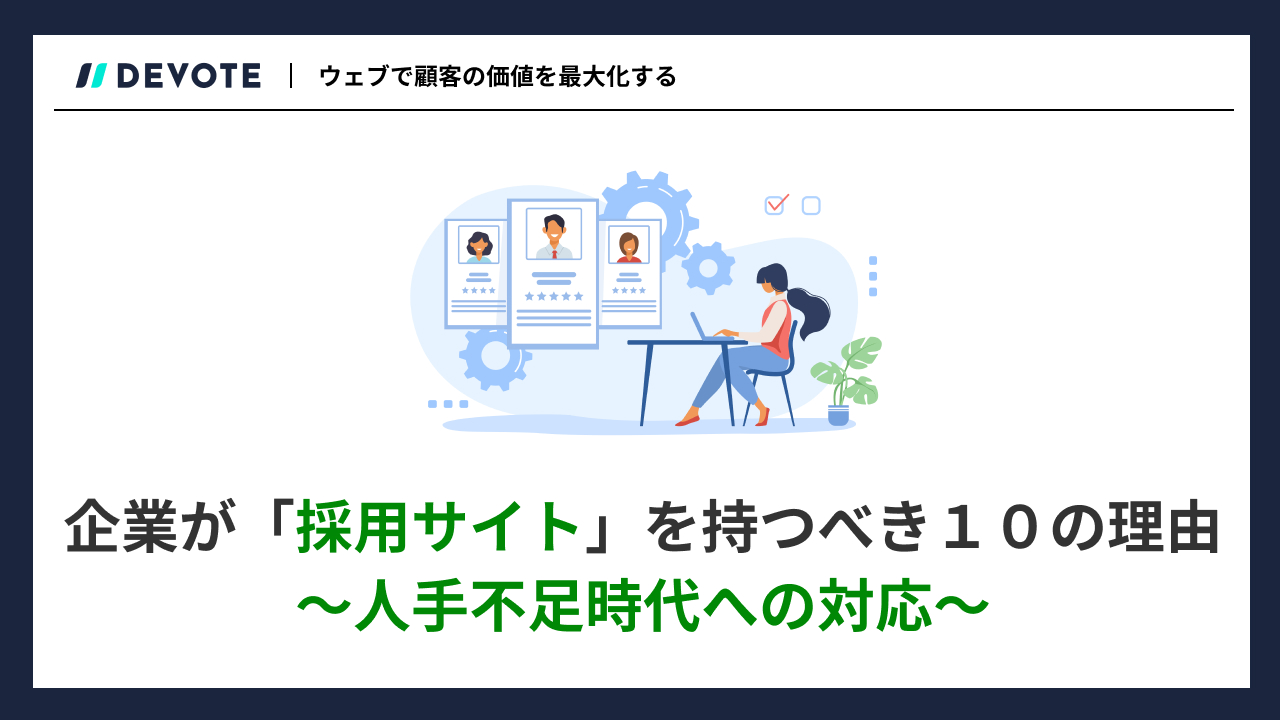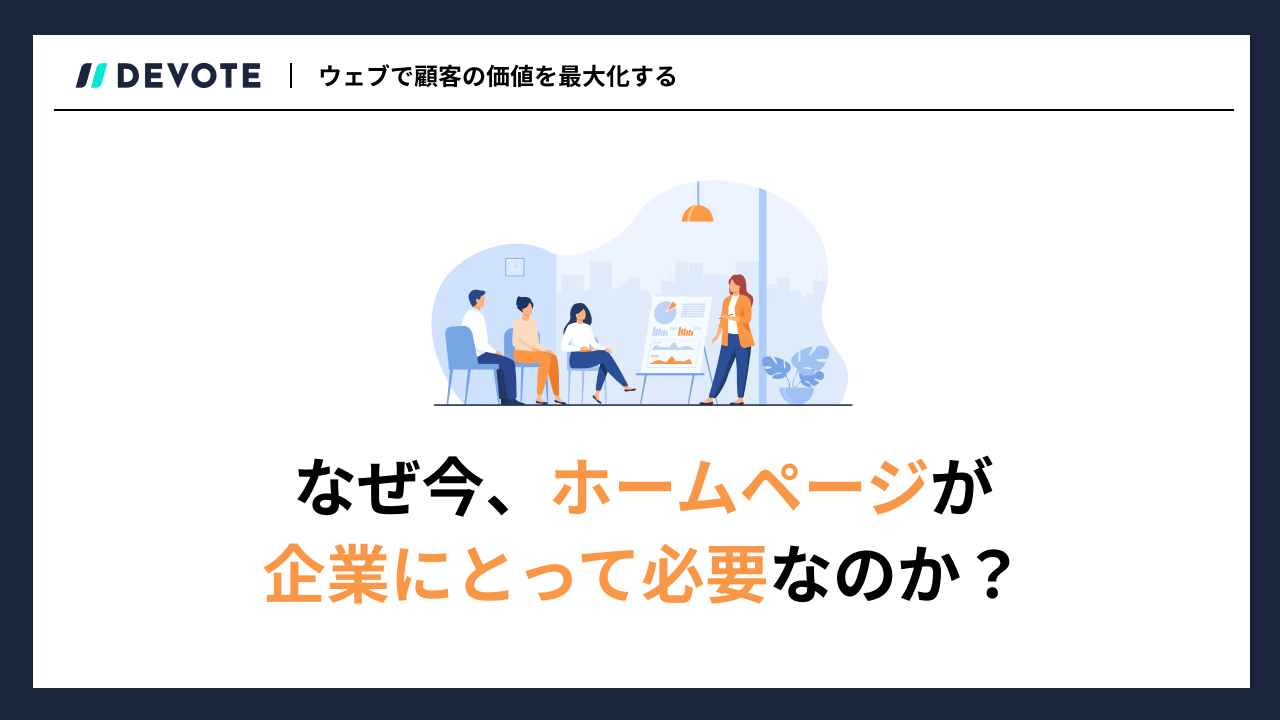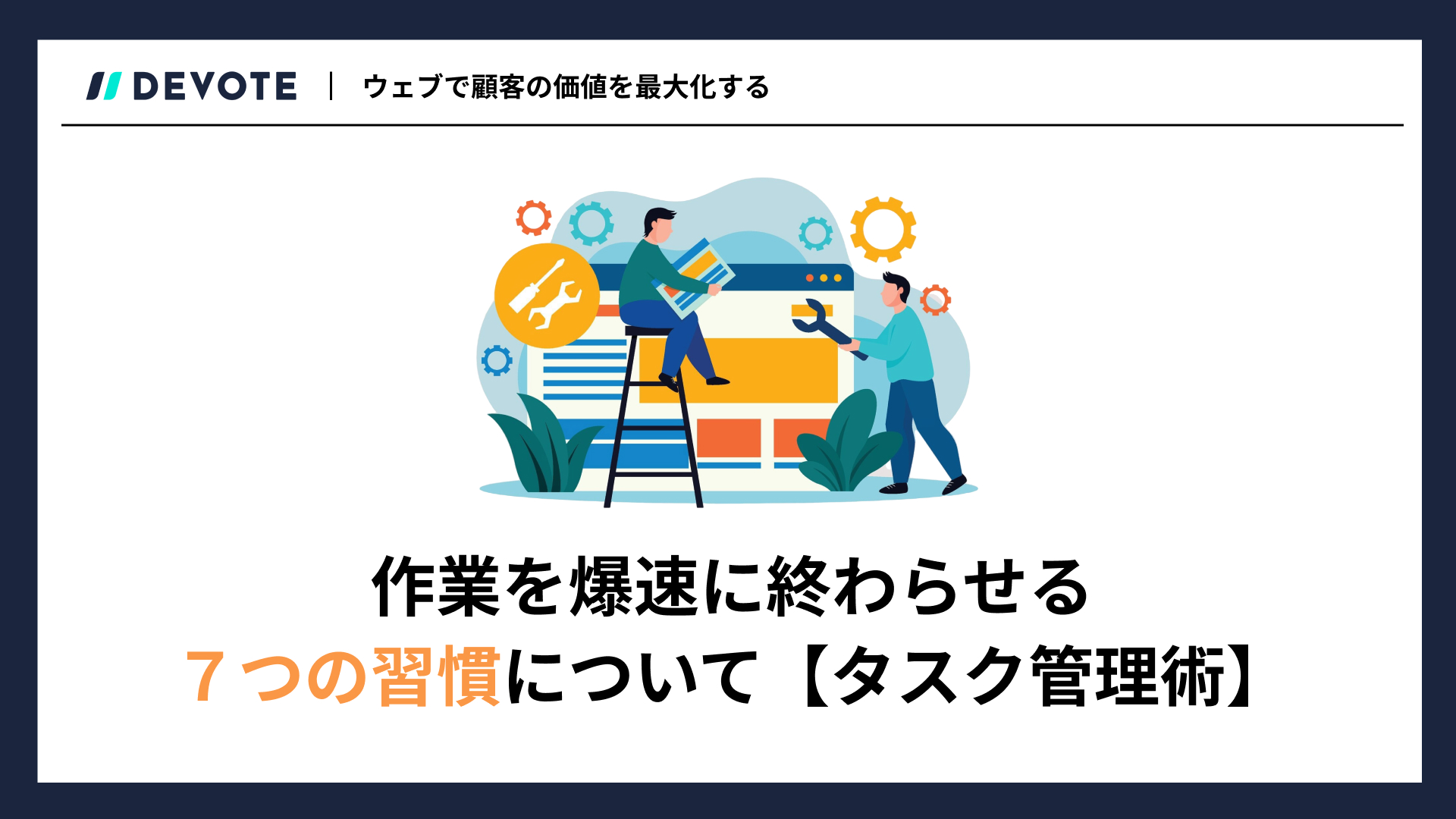気の遣いすぎが招く生産性の落とし穴

仕事で「気をつかう」ことは、相手との信頼関係を築くうえで大切な要素だ。とくにビジネスシーンでは、礼儀や配慮を欠かすことはできない。
ただその一方で、気をつかいすぎることによって、逆に仕事のスピードや伝達の明瞭さが損なわれてしまうこともある。
とくにチャットやメールといったテキストベースのやりとりでは、過度な気づかいが「遠回しな表現」や「無駄な確認」を生み、コミュニケーション全体の効率を落としてしまいがちだ。
今回は、そんな「気をつかいすぎ」が招く問題と、その対処法について考えてみる。
気をつかうこと自体は良いことである
まず大前提として、すべての気づかいが悪いわけではない。
相手に対する配慮は、社会人として必要な姿勢だし、思いやりのある関係づくりには欠かせないものだ。
ただし、ここで言いたいのは「もっと雑になれ」ということではなく、特に注意したいのは、テキスト上でのやりとりにおいて、無意識のうちに非効率を生んでしまうケースだ。
特にリモート環境の現代社会において顔が見えない分だけ余計な気づかいを加えてしまい、かえって伝わりづらくなってしまう。この問題を見過ごすとチーム全体の時間とエネルギーを浪費してしまうことになる。
気をつかいすぎが生む3つのデメリット
1. 時間のコストが増える
たとえば、何か相談したいときに「今お時間ありますか?」と確認してから本題に入る。一見丁寧に見えるが、これはワンクッション増えることで数秒〜数分のロスになる。この小さなやりとりが1日に何回も、1年で何百回も積み重なると、かなりの時間を消費してしまう。
「余計な確認」が、仕事のテンポを削いでしまうことがある。
2. 解釈のズレがそのまま進行してしまう
例えば、「できれば日程の検討していただけるとありがたいです」といった、やわらかい表現。相手への配慮としては悪くないが、人によっては「急ぎじゃないのかな?」と受け取られてしまい、もしかしたら相手によって優先度を下げられてしまう可能性もある。
本当は「早めに対応してほしい」内容だったとしても、表現があいまいだと後回しにされてしまう。つまり、気をつかいすぎた結果、意図が正しく伝わらないことがある。
3. 精神的な負担が増えていく
例えば、毎回のやりとりで「おはようございます」「お世話になっております」といった定型文から始める。これも一種の気づかいだが、社内のやりとりでは少し過剰になってしまうこともある。
繰り返すうちに、送る側も受け取る側も「めんどくさいな」と感じてしまいがち。せっかくのテキストのスピード感が失われてしまうのは、とてももったいない。
事前にルールを決めておく
たとえば「会議を入れるときは、空いていればカレンダーに直接入れていい」など、あらかじめルール化しておく。もしくは相談したい側を優先して「◯◯時に設定したのでお願いします」というメッセージのみでいい。そうすれば「今お時間いいですか?」といった確認を毎回する必要がなくなる。
そもそも論になってしまうが、事前にMTGが発生するかもしれないというタスク管理と共有ができていないことも原因としてある。あらかじめタスクの1つにMTGという作業を追加しておき、事前に「◯◯日◯◯時」と決めておけるのがベストだ。
提案型のコミュニケーションに変える
他にも「〇日は空いてますか?」ではなく、「〇日と△日の午後なら空いています。どちらかいかがですか?」と複数案を出す。
このように主導権をもちつつ提案することで、無駄なラリーを減らせることができる。いわゆる相手が「イエス・ノー」で答えられるクローズド型のコミュニケーションをする方が効率がいい。
定型文を減らす勇気をもつ
毎回「お世話になっております」「おはようございます」「おつかれさまです」と書く必要もない。社内やチームの相手ならいきなり本題に入っても問題ないことが多い。「今日は◯◯の件でご相談です」と一言だけで、十分に丁寧さは伝わる。
気をつかうことそのものは、やさしさの表れであり、ビジネスの現場でも必要な姿勢だと思う。でも、それがたまには逆に「伝わらない」「時間がかかる」といった本末転倒な状態を招いてしまう。
とくにテキストでのやりとりでは、簡潔さと明瞭さを意識することが、お互いのストレスを減らし、結果として関係性をよくする近道になる。
「気をつかう」は相手のためでもあるし、チーム全体の生産性にも寄与する。時間は有限であるし、勤務時間も1日で限られてくる。だからこそ、「伝わる」「進める」形で届ける工夫も同じくらい大切にしていくべきである。
コーポレートサイト制作ならご相談ください。
デボートはクライアントの悩みを共に解決する伴走型のWeb制作会社です。「Webサイトで集客をしたい」「採用できない」「人手が足りない」といった悩みをお持ちなら、ぜひお気軽にご相談くださいませ。